 Boxing Novelette ボクシング短編小説 Boxing Novelette ボクシング短編小説

|
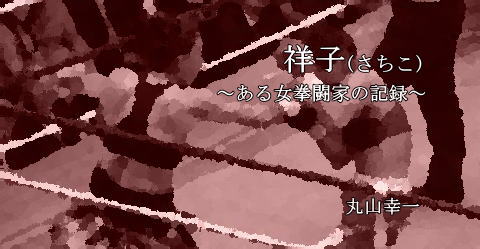 |
22
祥子から電話がかかってきたのは、私が病院を2度目に訪ねた1ケ月後のことだった。
「退院したのよ」。祥子の声が弾んでいた。
「矢嶋先生からあなたがきてくれたことを聞いた時、ほんとうに嬉しかった」。甘えるような声だった。私の中にも込み上げてくるものがあった。私の祥子に対する感情は、彼女が入院する前とは明らかに違っていた。「これからどうするんだ?」。「あなたに会いたい」。間をおかずに祥子から言葉が返ってきた。私の気持ちも同じだった。
私達が彼女の実家に近い街で出会ったのは、電話があった3日後だった。
「あたし太ったでしょう?」。それが祥子の第一声だった。
「健康になった証じゃないか」と応じた私に、祥子は小さく頷くと、そっと私の手を握った。その手を握り返した私に祥子が言った。「あたし達、まるで恋人同士みたいね」。その言葉を聞いた時、私は反射的に手を放した。今思えば、まだ祥子を拒絶したかったかつての自分が、どこかに潜んでいたのだろう。そして私は自分のとった行為にうろたえていた。
けれども、「ごめんなさい」と、か細い声で謝罪したあとに続いた言葉が、さらに私を動揺させた。
「じゃあ、今日、抱いてもらえないの?」。首を傾げながら、祥子はそう言ったのだった。そして、そんな祥子に、私も激しい欲望を覚えていた。
それからどれほどの時間が経過したのだろう。私は私自身に打ちのめされていた。
「いいのよ」。祥子の慰めの言葉が辛かった。場所はホテルの一室である。彼女に欲望を覚えたはずの私の体はしかし、全く反応しなかった。ファウンデーションで隠されていた左手首の傷跡が浮き彫りになっていた。その傷跡にそっと右手を置きながら彼女が言った。
「私では駄目なのね」。
「そうじゃあないんだ」。弁解がましい私に祥子が言葉を重ねた。
「私はあなたと結ばれることで魂と魂も結ばれると思ったの。入院中、いつもそんなことを考えていた。でもあなたは、そうなりたくなかったのね」。その言葉が私の心をさらに突き放した。
祥子と別れた私は、浅草に向かった。一角に宿が軒を連ねていた。無造作にその中の一軒に足を踏み入れた。部屋に通された私に愛想笑いを浮べた女将が「どんな女の子がよろしいかしら」と畳かけてきた。15分ほどして部屋に入ってきたのは貧相な40女だった。しかし、私の体は、そのやせぎすの艶を失った肉体に反応していた。
その一夜以来、祥子からの電話は一度もなかった。私も彼女にどれほど、電話をかけようとしたことか。けれども、受話器の前で、私の指は凍りついた。そういう毎日が繰り返され、半年が過ぎた。既に木の葉が色づく季節になっていた。
――正午近くに空気を切り裂くような電話のベルが鳴った。受話器を受け取るといきなり高井の声が聞こえてきた。
「もう聞きましたか?」。
「どうした?」。
再び彼が今度はしっかりとした口調で言った。
「じゃあ、まだ聞いていないのですね」
「何をだ?」。
「祥子が死にました」。
言葉を失った私に高井が早口で続けた。
「昨夜です。祥子の母親からさっき連絡がありました」。
咄嗟に私は自殺を確信した。が、高井が口にした死因は信じられないものだった。
「母親の話によると、溺死らしいんです。場所は自宅の浴槽です」
そんなことがある得るのだろうか。
「実は」と高井が言いかけて言葉を切った。
「・・・昨日、二人で飲んだんです。で、10時頃別れて・・。祥子が亡くなった時間は夜中の3時頃だそうです。母親が発見した時にはもう心臓が止まっていたらしいんです」。
「母親がそう言ったのか」。
「ええ、とても冷静に話してくれました」。
教会で葬儀が行われたのは、その翌々日だった。高井と共に参列した私は一足早く、教会を後にした。その夜、床についていた私は高井の電話で起こされた。高井は酔っていた。よく回らない舌で高井が言った。
「祥子が死んだ日、僕は祥子に二度と会わないと伝えたんです。その言葉が祥子を追い詰めたんです」。
電話の向こうで高井は泣いていた。
「じゃあ自殺だったのか?」。
「ええ、風呂の中で手首を切って・・」。
高井は祥子の母親からはっきりと聞いたのだった。
「できることなら僕も死にたい」。酔いが言わせた言葉に違いなかったが、無視することはできなかった。高井の居場所を尋ねた。何度も聞いた私にやっと答えた酒場に、私はタクシーを飛ばした。
祥子の自殺を自分の責任だと、泣きながら語った高井が、哀れだった。しかし、彼がいる酒場が近くなった時、突然、ある疑念が突き上げてきた。
|
|
|
|
|
|
 |
|