 Boxing Novelette ボクシング短編小説 Boxing Novelette ボクシング短編小説

|
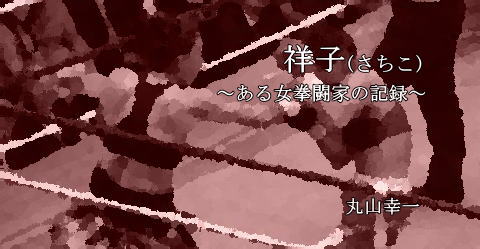 |
20
I病院は、よく整備された広大な庭を持つ精神病院だった。その庭での面会を許可されたのは、彼女の母親の元を訪ねてから、1ケ月ほど経った時だった。「病院の方で面会を許可してはくれないだろう」という母親の判断に反し、私と是非会いたい、と言ってきたのは主治医の矢嶋医師だった。こうして私は、祥子の母と連れ立ち、I病院を訪れたのである。
改めて自己紹介をした私に矢嶋医師は、「祥子さんからあなたのことを伺っていました」と笑顔を返してきた。彼はまだ30歳代半ばと思われる表情豊かな青年だった。「祥子さんが何と言っていたのか不安を覚えます」。身構える姿勢で応じた私に医師は屈託なく言った。「まあ、私に話したあなたのことは、そのまま受け止められるわけではありませんから。むしろ彼女の話を何かのサインと解釈するケースの方が多いのです。だから・・」。そこで言葉を切ると、医師はおもむろに「時間はございますか?」と私に向き直った。矢嶋医師は、待合室の長椅子に腰を下している母親に「もう少し丸谷さんにお聞きしたいことがありますから」と言い置くと、「庭に出ましょう」と私を誘った。
芽を吹き始めた桜の木の下のベンチに座った医師は思いがけない話を始めた。
「私は祥子さんの病状についてお話することはできませんが、・・」と前置きしながら医師が語ったのは祥子の母親の信仰についてのことだった。
「自分の肉欲を律した生き方以外にキリスト者としての道はない」と母親は以前、強い口調で語った。彼女が指した肉欲とは、性的な対象だけではなく、テレビに興じたり、エンターテイメントの小説を読みふけることもその肉欲の対象なのだった。極論すれば、肉欲を律した生き方とは、2000年前のイエス・キリストが弟子を連れて教えを垂れながら、乞食同然に彷徨った生き方である。キリスト教に疎い私は、母親のそうした言葉に沈黙するしかなかったが、母親は矢嶋医師にも同じ内容を力説していたのである。
「私は長崎の出でしてね。実は代々カトリックを信仰してきた家系なんです。いわば隠れキリシタンの家系です」。医師は小さくそう言うと、「でも私の信仰なんて祥子さんのお母様から見ると異端に映るのでしょう」と声に出して笑った。「物心ついた時から教会は馴染み深い場所で、幼くして洗礼を受けさせられましたが、高校に上がってからの私は学校をサボって、映画ばかり観ているような子供でしたから・・。祥子さんのお母様のように、物質文明に取り込まれない精神生活を確保しようとしている人、というより、彼らがより所としている宗派は世界には数多く存在するんです。そういう宗派には近代医療など文字通り異端になる。輸血も自然の摂理に反した悪魔の所業ということになる」。自分の饒舌に気付いた医師は苦笑しながら、結論を急いだ。
「祥子さんが精神の健康を取り戻すには、何よりも周囲の協力が必要なんです」。
私は医師の言葉に困惑した。その「周囲」が明らかに私を指していると思われたからである。私は医師からの連絡に応じることを約束すると、祥子の母親を残して病院を去った。
私が矢嶋医師と2度目に会ったのは、2週間後だった。私はその前夜、夢にうなされた。夢の中の私の前に襤褸(ぼろ)を身に纏った男が立っていた。
「あなたはイエス・キリストですか?」。私のその問いに男は静かに答えた。
「私の顔は仮面に過ぎない。この仮面を剥げば私が誰であるか、お前にわかるだろう」。
私は男に襲い掛かり、仮面を無理矢理剥いだ。新しい顔がむき出しにされた。
その顔は、私の顔だった。
私の家から病院までは4キロの距離に過ぎなかった。その距離を私は歩いた。歩きながらこれまでのことを、前夜の夢も含めて小1時間の時間の中で咀嚼してみたかった。祥子の母親によれば、祥子の精神がにわかに変調をきたしたのは、流産した直後だった。祥子は退院した翌日、母親の目を盗んで外出すると彼女が子供の頃から親しんでいた、カトリック教会を訪れた。
「あの子が神父様に付き添われて戻ってきたのは2時間ほど経ってからでした。あの子は神父様にこう言ったのだそうです。“私は大天使ガブリエルから精霊を受けて子を宿しました。でもその子は私の体内から抜け出ていってしまったのです”。そう言うと、自分のスカートをたくし上げ、流産したお腹を見せたのだそうです」。
大天使ガブリエルとは、母親の説明によれば、聖母マリアだけではなく、バブテスマのヨハネの母にも降臨して受胎を告げた天使なのだという。
「驚いた神父様は真剣に、“受胎を告知されたのはいつのことか”と娘に尋ねたのだそうです」。
それから1時間ほど神父と祥子の間でやりとりがあった。あくまでも大天使ガブリエルに、自分も告知されたと言い張る祥子に神父は彼女の明らかな精神の錯乱を悟った。こうした経緯の後、祥子は千葉県の病院に送られてきたのである。
この話を聞いた時、私が感じたのは精神病棟に入ることを受け入れた祥子の絶望よりも、彼女の悪意に満ちたユーモアだった。そうであったなら、彼女の精神が錯乱状態に陥っているはずはなかった。
私は昨日見た夢のことを考えた。聖母マリアに受胎を告知した大天使によって子を身籠ったという痛烈なブラックユーモアは、キリストを自称する男の仮面を剥がした後に、私の顔が現れた、昨夜のたわいない、しかし不気味この上ない夢とごどこか共通するものがあった。が、私は頭を振ってその思いを振り払った。既に病院の敷地内だった。
その日、私が通されたのは矢嶋医師の診察室だった。彼は長い時間をかけて祥子と私との数年に渡る話を執拗に尋ねた。しばらく時間が経過した後、医師はおもむろに口を開いた。
「この前もお話した通り、私の判断を今、あなたにお教えすることはできません。実際、私と他の医師の間でも判断が異なることは決して稀ではないのです」。
彼が私に要求したことを率直に解釈すれば、情報の提示だった。そして私は医師の要求に忠実に応えたつもりだった。医師が口にできない病名は何なのか。神父は明らかに、祥子という人格は引き裂かれてしまっているに違いない、と解釈したはずである。しかし、私は祥子の人格が明確な分裂を起こしているとは到底、思えなかった。
確かに祥子の虚言癖やある種の行為は常軌を逸していた。ただ、彼女がロスで起こした自殺未遂は、それまで彼女に抱いていた私の判断を覆していた。また高井が語った話を総合すれば、彼女の内面には自分に対する嫌悪の感情が歴然と残っていた。彼女が自殺を企てたのは、高井に「自分は自己中心で本当に駄目な人間なんです」と訴えた直後だった。
私が出会ったのは、その後の彼女だったが、私を困惑させ祥子は、ある種の人格障害の兆候こそ感じられたものの、決して分裂した自己を持つ女ではなかった。
彼女の中には明らかに、自分を懐疑する心が残っていた。ただ、彼女は自分を突き上げる突発的な感情を制御できなかったのだ。その果てにまた深い嫌悪に陥る。同時に無軌道な行為を正当化してしまいたい祥子自身も、心の奥底に存在していたに違いない。彼女に罠を仕掛けられた自分を私は何度も感じていた。けれども私以上に祥子自身が、自分の仕掛けた罠の中でもがき苦しんでいたのである。
「祥子さんがここに来てから2カ月ほどになりますが、トレーニング・ルームではいつも3,4人の弟子にボクシングを教えているんです。“それは何という練習なの”と尋ねると“シャドーボクシングです。先生、ボクシングのこと知らないのね”と笑われました。・・・とにかく表向きは元気です。仲間も沢山いますしね」。矢嶋の言葉に、私は力を得た。
「じゃあ、退院は近いのですか」と尋ねた私に沈黙で答えたものの、その医師の明るい表情が印象的だった。
「結局、祥子さんは私に何を求めたんでしょう?」。医師の明るい表情に意を強くした私は、聞いた。
医師から返ってきたのは、再びの沈黙だった。
|
|
|
|
|
|
 |
|