 Boxing Novelette ボクシング短編小説 Boxing Novelette ボクシング短編小説

|
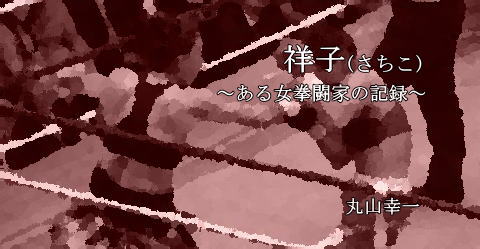 |
16
高井の疑いを込めた言葉に、私は唖然とした。
「だって、祥子が帰国してから1ケ月も経っていなのだろう? 仮りに祥子と関係があったとしても、おかしいじゃないか」、そう答えた私に、高井が怪訝は表情で言葉を継いだ。
「いえ、祥子が帰国したのはもう4、5ヶ月も前になります。僕が彼女と出合ったのが去年の9月でしかたら」
私と祥子と高井との関係を思い浮かべ時、私は突然、難解なパズルが解けた気がした。私が取材を通じて感じた高井は、こちらが投げかけた問いにもじっくりと内容を咀嚼し、的確な言葉を選んで答える青年だった。私は彼に、細やかな神経と温かい人柄を感じていた。その高井が実は、粗暴で思いやりのかけらもない人物だと私に訴えたのは無論、祥子である。
私は高井に、祥子から聞かされていた高井に関することを思い切って話してみた。しばらく間があった後、高井が言った。
「・・・確かに、僕の取った態度で祥子が傷ついたことは色々あったと思います。でも丸谷さんが祥子に聞かされた話って、事実と相当違っているんです」。
彼が語った話はこんな内容だった。
祥子に好意を抱いた高井は、恐る恐る食事に誘い、祥子が求めに応じたことから二人の恋は始まった。やがて半同棲のような形となり、さらに祥子はほとんどどの日を高井のアパートで過ごすようになった。
「僕にとっても、本当に満たされた日々でした。彼女に変化があったのは、僕がタイトルを取って間もなくしてからです。最初はチャンピオンになった僕を、誇らしく思ってくれていたんですが、初防衛戦が決まり、試合の日まで1ケ月を切った頃から様子がおかしくなったんです」。
高井はそこまで言った後、息を整えると再び話し始めた。
「僕は相手のビデオを克明に見てボクシングを組み立てるタイプで、そうして元来、臆病な僕はやっと試合に臨むことができるんです。ですから試合まで後1ケ月なんて時はもう毎日が必死。それが防衛戦ともなればなおさらです。そんな僕だから、彼女が話しかけてきても上の空なのはしょっちゅう。そうなると祥子は、耳元に口を当て大声で自分の言いたいことを主張したりする。ジムワークから戻ってきて、軽い食事を済ませて体を休めようとすると、今度は纏わりついてくる。布団に入れば体を求めてくる。・・それでもそんな彼女が愛おしかったんです」
高井は再び一呼吸置いてから、さらに続けた。
「減量に入ってからが大変でした。10キロ以上も落す必要があったから、減量態勢に入ると、全く祥子を抱く気にもなれない。口も渇くからキスをせがまれても、うんざりするだけです。ボクシングジムに通ってる祥子のことだからボクサーの精神状態なんて当然、理解してくれるものと思っていた。でも彼女はわかろうとしなかった。試合の1週間前のことです。減量が苦しくてふらふらしながら帰ってきた僕に、祥子が作ったのは300グラムもあるハンバーグです。“これを食べて元気になって”と言うんです。冗談じゃない、と僕が言葉を荒げると、いきなりハンバーグを投げつけてきた。なんでこんなやり取りをしなきゃならないのか。そう思うと腹が立って、つい祥子の頬を叩いてしまったんです」
そこまで話を聞いて私は思わず笑った。
「つまり僕のように叩いたんだ」。私が混ぜっ返すと「いえ、僕は1発だけ。あなたと一緒にしないでください」と高井も笑いながら応じた。「でも祥子は、君に犬のように扱われた、その上、同僚まで呼んで彼女を陵辱しようとした、と言っていた」。私は初めてそのことに触れた。高井は長いこと目を伏せたまま黙っていたがやがて意を決しとように顔を歪めながら答えた。
「それは本当です。結局、僕はタイトルを防衛できなかったでしょう。その翌日、何か祥子を無性に侮辱してやりたくなって・・・。同僚を呼んで“この女お前が欲しけりゃ、くれてやるよ”と言ったんです。その同僚は少し経って、出て行きました。何にもしないでね。何でそんなことをしたのか。負けたのは僕が弱かったからです。でも祥子がやったことは、まるで僕が負けるのを望んでいるような行為ばかりでした。その彼女に僕が抱いたのは、密かな殺意でした。・・彼女を侮辱することで、僕は自分の中に芽生えた殺意を消そうとしたのだと思う。多分・・」
私も高井もその在り方は違っていても、祥子に殺意を抱いたのである。やりきれない話だった。
「でも僕はこう思うのです。僕にも丸谷さんにも彼女は処罰されたかったんじゃないか、と」。高井がぽつりと言った。
「処罰?」
「ええ。あなたと祥子とがどれほどの関係だったのか。僕にはよく分からない。ただ、愛されたいと思ったのは事実でしょう。でも彼女が求めている愛情って、普通とは違うんです。・・底なしというか。僕の試合が迫り、減量に入って祥子に今までのように気持ちを割けなくなると、恐らく彼女は見捨てられたような気分になるのだと思う。僕がその彼女に応えてやる余裕がないのは、彼女も頭ではわかっているんです。でもそんな理性を、見捨てられる、という不安が押しのけてしまう。その結果、さらに執拗に僕に愛情を迫ってくる。だから、試合が終わり、僕の気持ちが安定すると、祥子は逆に冷酷になる。・・その繰り返しの末、僕はやっと取ったタイトルを、一度も防衛できなかった。それを彼女のせいにするのが卑劣なこととは承知していますが、どうしてもその思いが僕の中に残って・・。彼女もまた、試合に負けたのは自分のせいだと感じているんです。だから処罰を望むのです。どんな形でも処罰されれば愛情が繋ぎとめられる、そう思うからこそ、処罰を望むのです」
――それはおぼろげながら感じたことだった。私と祥子と高井を結ぶパズルの答え。それこそ今、高井が語っていたことに集約されていた。確かに彼女は処罰を欲していたのだ。処罰することで私にも高井にも深い負い目が生じてくる。その負い目のために処罰した男達はもっと祥子を深く愛さなければならなくなる。祥子はそうして多くの男に、いや、自分を愛して欲しい対象に罠を仕掛けてきたのだろう。
「でも君はよく彼女と別れることができたね」。ため息混じりに私が吐いた言葉に、高井が反応した。
「とんでもない。それから僕と祥子の地獄のような第2ラウンドが始まったんです」
高井はタイトルを失うと現役時代の後援者の勧めでロスへと旅立った。ボクサー時代に鮨職人として腕を磨いていた高井が選択した、第二の人生だった。
「実を言うとロスへ行けば祥子と決別できるという気持ちもあったんです。・・その店に祥子が現れたのは僕と別れてから1年ほどした時でした」。
こうして高井は祥子との「地獄の第2ラウンド」を語り始めたのだった。
|
|
|
|
|
|
 |
|