 Boxing Novelette ボクシング短編小説 Boxing Novelette ボクシング短編小説

|
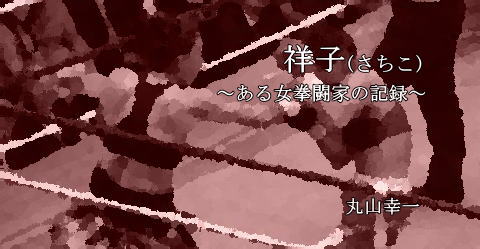 |
18
高井の言葉から推測すれば、私が初めて祥子に会ったのは彼女を自分のアパートから追い払った3年ほど後のことになる。さらにそれから2年の歳月が経ち、私と高井は奇しくも祥子を介して再会したわけだ。
2年前、私は祥子の話に一度は深い憐憫を覚えた。やがてそれは忌まわしい感情に変わっていった。高井の口から出た、東京とロスにまたがる祥子との交情も、私のその感情を深めるだけだった。
高井の話と私に対する祥子の行為は、彼女を鵺(ぬえ)のような得体の知れない存在に仕立て上げていた。
「祥子が求めていたのは処罰なのではないか」と高井は言った。確かにそうなのかも知れなかった。試合を間近に控え減量に苦しむ高井の神経を逆撫でにし、たった一度、彼女を取材しただけの私に纏わりつき、困惑させた。ある時はすぐに発覚するような幼稚な虚言で辟易させた。その果てに、私も高井も彼女を打ち据えた。祥子が望んでいたのは、まさに我々のそうした行為であり、処罰に違いなかった。「アンという女に会ったんだね」。私は唐突に高井に問うた。「君が祥子を追い払ったのは、アンが原因だったんじゃないのか」
「祥子は、あなたにもアンの話をしていたんですね」。驚いた風もなく、高井が答えた。
自殺未遂から4か月ほど経った時だった。高井が帰宅すると、祥子はアンとワインを飲んでいた。
「綺麗な人でしたよ。でもその頃の僕はただ疲れていて・・・。祥子との生活にも自分にも疲れていたんです。だから、彼女を美しいと思った以外に何も感じませんでした。ただそれからアンは頻繁に僕のアパートに来るようになったんです」。
「アンは自分のことをボクサーと言っていたの?」
「ええ、だから僕にも色々身を接しながら質問しました。コーナーに詰められた時の回り方とか、右を打つ前のジャブの出し方とか・・。でもそんなアンが僕には疎ましかった。アンにとっては、僕は小さな国でタイトルを取り、そのタイトルを半年も維持できなかった男です。にもかかわらず、祥子はそんな僕のことを得意気にアンに吹聴していた。そう思うとやり切れなかったんです」。
ある日、仕事で疲労困憊した高井が自室の見たものは予想もしていなかった光景だった。
「アンと祥子が、全裸のままベッドで眠っていました。二人が何をしていたのか。それは僕にも想像がつきましたが、僕はそのままにしておくつもりだったんです。ただ薄明かりの中で僕が二人の裸体に見たのはひどい発疹だったんです。その時、僕はすぐその発疹の原因が分かりました」
高井が思い当たったのはドラッグの常用だった。喘息患者に使われる治療薬に含まれるエフェドリンを抽出して水に溶かし、血液に注入すると交感神経を刺激し、著しい催淫効果を発揮する。それは当時、麻薬の取り締まりが厳しくなったロスで流行っていたドラッグだった。そして常用し続けた後遺症が、興奮した後、上半身に出来る発疹だった。高井はその二人を即座にアパートから追放したのだった。
その話を聞いて私はようやく、祥子の発疹の原因を知った。それは高井に陵辱された心の傷ではなかった。原因は薬物による後遺症だったのだ。その高井の話を聞いた私は、激しい疲労を覚えていた。しかもその祥子が今、私の子供を孕んだと、言い通しているのである。
高井のアパートを追われた祥子は帰国し、改めてジム通いを始めた。そして私と、取材を通じて知り合い、数ヶ月すると再びロスへと旅立って行った。プロボクサーとなるために・・。しかし、眞の目的はアンと再会するためだったのだ。「丸谷さんじゃなければ、祥子が身籠った子の相手は誰なんでしょうね」
高井は真面目な表情で呟くように言った。
「そりゃあ、祥子の作り話に決まっているじゃないか」。
しかし、高井の返答は私を驚かせた。
「僕のところへ顔を見せたのが5ヶ月ほど前です。だから、それからすぐ誰かと関係したことになる。相手は僕が知っている誰かも知れない。そんな気がするんです」。
そう断言した高井に私は微かな嫌悪感を抱いた。いつも自信なさげで他人を慮っていた高井の断定的な口調が、これまで私が抱いていた高井の印象と明らかに違っていたからだ。しかし私は、高井の言葉をよそに酒席に別れを告げた。
それから1年が経った。祥子を取材した当時はまだ珍しかったプロを目指す女性ボクサーの数はにわかに増え、関西では初のジム対抗戦が行われたことが専門誌で報じられたのもその頃だった。
この1年間、私は祥子のことを、ことある毎に思い起こしていた。果たして祥子は本当に身籠ったのだろうか。仮にそうだとしても、彼女はお腹の子をどうしたのだろう。疑問はまだあった。高井に多くの負担をかけたまま、さっさと帰国した祥子の母親・・・。自分に執着する一方で、自分を死に至らしめる直前まで痛めつけようとする祥子の自傷行為。そして、アン・・・。
彼女が立っているのは、いつも危うい場所だった。彼女を取り巻く環境が、さらに彼女の居場所を危うくしていた。そうは思っても、私は何の行動も取りはしなかった。むしろ私が望んでいたのは、彼女との関係を絶つことだった。
私の家に祥子が唐突に訪ねてきた時、私の母は私を詰問するように言った。
「祥子さんはあなたに救いを求めてきたのに、あなたは取り合おうともしなかった・・」
祥子も私に手紙の中で訴えていた。「誰にも愛されない自分。そんな自分を人間は愛することができるのかしら。人から認められ、求められる自分しか人は愛することができないのじゃないかしら。そうなら、人から愛されることを知らない人間がどうやって自分を愛することができるのかしら・・」。
そんな祥子に、私は取り合おうとしなかった。母の言葉も事情を知らない老女の感傷にしか思えなかった。そして私の行為は、精神に異常を感じた祥子に対する私が取った最善の自己防衛策だった。
その自分が崩れかかっていた。私はかつて友人のドストエフスキー研究家が言い放った言葉を思い起こした。
「生きる意味を求めようとはせず、自分だけを愛し、徒に時間を費やしているお前こそ卑劣漢ではないか」。
それは酒に酔い、祥子の顔を強か叩き、その自分に打ちひしがれて私自身に現れた幻影の中の友人の言葉だった。
何日か経ち、春の気配が感じられたある日、私はAジムに連絡を取り、祥子の実家の電話を聞いた。「祥子が入門する際に書いたものだから」という注釈付きの電話番号だっただけに、期待もしないでプッシュホンのボタンを押した。
「はい佐川ですが」。
電話の向こうから聞こえてきたのは、祥子の母親と思われる中年女性の声だった。
|
|
|
|
|
|
 |
|