 Boxing Novelette ボクシング短編小説 Boxing Novelette ボクシング短編小説

|
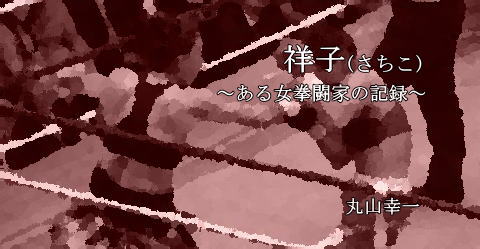 |
17
王座を陥落した高井が選択した第二の人生は、ロスで鮨職人として働くことだった。
高井によれば、祥子がその店に現れたのは、自身が異国に腰を落ち着けてから1年ほどたった時である。
「祥子がいきなりカウンターの中にいる僕の前に案内されてきた時には、本当に慌てました。店の中では彼女は客ですから、丁寧に応対するしかない。でも、こっちは疑心暗鬼です。緊張もする。一体、祥子が何を話しかけてきて、僕が何を答えたのか。覚えてはいません。で、30分もたったときです。彼女がいきなり声を上げて泣き出したんです」。
いかにも祥子のやりそうなことだ、と妙な納得をしながら、私は高井の話に耳を傾けた。
「すると近くにいた常連の女性客が彼女ににじりよって、祥子の背中をさすりながら彼女に問いかけだして・・・。二人が何を話していたのか。やっと日常会話ができる程度の僕の英語力ではよくわかりません。ただ、僕はその時、祥子が実に流暢に喋っているのを見て感心していたんです。彼女が英語を話せるなんて知りませんでしたから。ミッション系の学校に通っていたのだから不思議はないのですけどね・・・まあ、そんなことをボーッと考えていたら、突然その客が僕を指しながら、“あなたはこのアメリカで働く資格はない”と糾弾したんです」。
白人の中産階級とおぼしき中年女性が高級志向のある日本料理店で、相手を指差して非難の声を上げるのはよほどのことである。
「僕はもうパニクッちゃって・・。そしたらチーフがその客をなだめた後“もう今日は上がれ“と救いの手を差し伸べてくれましてね」
身支度を整え、店から出てきた高井は、その自分を待ち伏せしていた祥子の眼差しに出合った。そして先ほどの涙が嘘のように満面に笑みを湛えながら高井に近づいてきた。
「で、彼女はいきなり、こう切り出したんです。“あなたの働く姿はとてもセクシーだった。だからちょっと困らせたくなっちゃったの”」
高井はそんな言葉を無視して、力なく、白人女に祥子が何を話したのかを聞いた。
「カウンターの中にいる男は私を友人に売ったの。でも私はあの人をまだ愛していたから、何とかそいつの元を逃げてこのロスにやってきた。でもあの人は私に冷たくするだけだった。そう言ったのよ。そうしたらいきなりあなたに向かって怒鳴りだしたから、私の方が慌てちゃったわ」。
それが祥子の返答だった。
ややあって高井が私に言った。
「その話を聞いた時、僕がまず思ったのは、自分はあの店で再び働くことが可能なのか、ということでした。でもタイトルを失った後に祥子に抱いたような殺意は起きなかった。むしろ僕の中に込み上げてきたのは、何て可哀想な女なんだ、という感情でした。すると彼女は信じられない反応を示したんです。“あたしはとんでもないことをしてしまった”と言った後“あたしは自己中心で駄目な女なんです”。目に涙を溜めて“もう死にたい”と・・。僕はまた祥子の芝居だろうと思いながらも、そのまま放っておくこともできず、彼女が泊まっているホテルに送っていったんです。もし困ったことがあったら力になるからと、僕の住所を書いた紙を手渡して別れたんです」。
それは、私が抱いていた高井の人間そのままのエピソードだった。
「その翌日でした」。高井が性急に言葉を継いだ。
「帰宅した直後に病院から電話があったんです。完全には分かりかねたのですが、要するに“あなたの友人が深い傷を負った。だから直ぐに来て欲しい”という内容でした」。
直ぐに駆けつけた彼にERの担当医が説明したことは、それが明らかな自傷行為であること。つまり祥子は自殺を企てたのである。
「左の手首はもう少し深ければ致命傷になっていたほどの傷でした」。
祥子が自殺を企てた。結果的に未遂に終わりはしたが、手当てが遅ければ死に至るほどの深い外傷だった。
私が認識していた祥子は決して自殺などできないはずの女だった。祥子は、いつも自分だけを哀れみ、他人のことなど一切、斟酌しない徹底的に自己中心な性格の人間だった。防衛戦が近づきナーバスになった高井の心を、無理矢理自分に振り向けさせようとする極めつけのワガママ女だった。そうした性向の人間は、決して自殺などしない。それが私の認識だった。
「つまりそれは君を自分の方に向かせるための狂言ではなかった、ということ?」。
私の問いかけに高井が答えた。
「もし狂言ならもっと自殺を仄めかしてくるはずでしょう」
「でも病院が君に連絡できたのは何故? どうして第三者に彼女が自殺を企てたことがわかったの?」
畳み掛ける私に高井が苦笑しながら説明した。
「ドアの下から血が流れ出していたのを見たボーイが、責任者に連絡するかして部屋を開けた。狭い部屋なので彼女の手首から流れていた血を認めるのは簡単です。それで、すぐに救急車を呼んだ。部屋のテーブルの上には僕の住所と電話番号が書かれた紙が乗っていた。そんなところです」。
それでも私には疑問が残った。高井が書いた紙を発見者にわかるように置いたのは、最初から助かることを前提としたからに違いない。それにホテル側が警察に連絡をとらなかったことも、私には腑に落ちなかった。要するに私に祥子が本気で自殺をする女とはどうしても思えなかったのだ。しかも私は彼女に残っているはずの手首の傷跡も見ていない。私は高井の話を聞いているうちに、祥子と高井が二人で私を陥れているのではないか。そんな疑念に捕らわれていった。
高井の話はまだ続いた。彼は結局、その店を解雇された。
「チーフの紹介で別の日本料理店に何とか職を得た僕が、第一に考えたのは祥子のことでした。彼女の実家にはすぐ連絡を取ったのですが、母親がやってきたのは祥子の容態がすっかりよくなったころです。にも拘らず、母親が滞在したのはたったの3日でした。で、僕が手配したホテルに祥子も身を移した時、驚いたことに“この子のことを宜しくお願いします”と、僕が彼女の面倒を見るのが当然であるかのようにペコリと頭を下げたんです。病院で祥子が母親に自殺未遂の原因を語ったのか、それもわかりません。今でも僕はその原因を知らないのです。とにかく、祥子は僕の前に姿を見せたかと思うとすぐにあの騒動です。こっちは何が何だかわかりもしない。それなのにやってきた母親は、僕に祥子を託すと逃げるように日本に帰ってしまったんです」。
しかも高井が立て替えていた1万ドルを超える病院の費用も、未払いのまま帰国したのだという。ほとんど無一文になった高井が選択したのは、祥子と一緒に暮らすことだった。
「一緒になればまた同じことの繰り返しになる。そうは思っても、僕は祥子を見捨てることはできませんでした・・・祥子にこれ以上、関わりあいたくない感情をむき出しにしたまま帰国した母親が、僕になおさらそういう気持ちを起こさせたんです」。
その祥子を、高井がアパートから追い払ったのは、半年後のことだった。
|
|
|
|
|
|
 |
|