 Boxing Novelette ボクシング短編小説 Boxing Novelette ボクシング短編小説

|
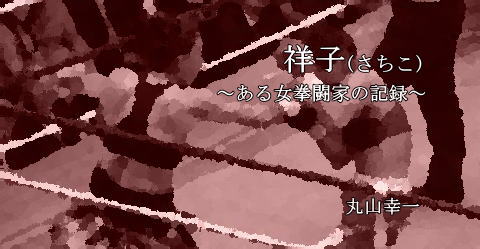 |
12
帰宅した時は11時をとうに回っていた。ドアを開けると、いきなり困惑し切った母の顔とぶつかった。何も言わずに居間に入ると、すき焼き鍋の用意をし始めた祥子がいた。
「帰ってくれないか」。私の言葉に祥子が振り向いた。
「君が帰らないのなら、僕が出て行く」。しかしその言葉を母が咎めた。
「こんな時間なんだから、泊まっていって貰うしかないでしょう?」。そう言った母の目は明らかに私を非難していた。それから3人の奇妙な食事が始まった。肉は最上級の霜降り牛だった。誰も口を開こうとはしなかった。
ただ、私と母によく煮えた肉を生卵を溶いた皿に運んでいる祥子の動きだけが、異様に活発だった。
沈黙に耐えかねた母が、口を開いた。
「それであなた達はこれからどうするの?」
「朝、祥子さんは帰るでしょう。それから詳しい話をします」。そう言った後、祥子を見た。私が出会ったのは、あの居酒屋で垣間見たのと同じ表情のない目だった。その時、やっと私は祥子の精神の異常さに気がついたのである。
翌朝、早く、私は祥子を最寄のJRの駅まで車で送っていった。帰宅した私を母が質問漬けにした。私はことの顛末をおおまかに話した。ただし、あの祥子の体を襲う湿疹のことを除外して・・。
「つまり祥子さんは、男の人にとてもひどい目に遭って、あなたに助けを求めてきた。それを取り合おうとしないばかりか、あなたも彼女を邪険に扱ったのね」。
「それは違うよ」。けれども、母は納得しなかった。
「祥子さんは必死にあなたに救いを求めてきたのでしょう? でなければ、いきなりウチにまで来る訳がないでしょう。あなたが言うように、二人の間に何もなければの話だけど」。私は母との話をいい加減に打ち切ると外へ出た。
外の冷たい空気を吸いながら思った。あの目が祥子の精神の異常を物語っていたのだ。そう考えれば、祥子のこれまでの行動が読めてくる。祥子の心はいつから病んでいたのだろうか。高井との出来事が原因なのか。それとも、それは単なる引き金だったのか。そう考えると私の頭は混乱した。
「あなたと何の関係もない人が何故、よりによって晩御飯の材料まで持って、いきなり訪ねてきたのかしらねえ」。
「分かりませんね」。
「だって、どう考えてもおかしい話じゃないの」。
「それを一番、感じているのは僕ですよ」。こんなやり取りは何日も続いたが、祥子が訪ねてくることは2度となかった。そして私も母も祥子のことは、記憶から消えていった。
|
|
|
|
|
|
 |
|