 Boxing Novelette ボクシング短編小説 Boxing Novelette ボクシング短編小説

|
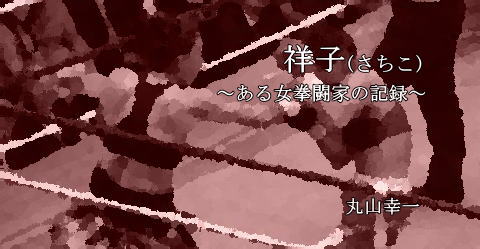 |
6
その言葉にたじろぐ私を気にも留めず、祥子はブラウスも脱ぎ捨てた。
ブラジャーだけを身に纏った祥子の体。肩から二の腕にかけて浮き立つ血管、小ぶりの乳房を包むブラジャーを押しのけるように腫れ上がった大胸筋、くっきりと幾重にも割れた腹部……。私が垣間見たのは、鍛え上げられた肉の塊だった。その苛烈な塊に私が抱いたのは、凶悪な印象だった。そして嫌悪を覚えた。
「触ってください」。祥子がまた言った。
私は意を決して彼女の二の腕を触った。祥子の口から小さな声が漏れた。その声を無視して肩に触れた。それから腹へと手を這わせた瞬間、「あっ」という叫び声と共に、私は大きく弾き飛ばされていた。すかさず「ごめんなさい」。祥子が小声で言った。
しかし、その表情は謝罪の言葉とは裏腹に憎悪に満ちていた。
私は茫然として彼女を見つめていた。私が触れた祥子の体は、単なる物質でしかなかった。が、その物質は思いもよらない反応を示したのである。冷静になって祥子の体をながめわたした私は、息を飲んだ。祥子の顔も首も腕も、いや祥子の個体の全てが真っ赤な湿疹で覆われていたからである。その時、彼女が私に自分の体を触れさせた意図を初めて理解した。
「こうなっちゃうの」。押し殺した声で祥子が言った。
「高井のアパートを飛び出してから、電車の中で男の人の体が触れただけで、湿疹が出るようになったんです。それが段々ひどくなって、今はこう……」
「それを見せたかったのか」。私は言葉を吐き出すと、部屋を後にした。
外へ出ると、すっかり明るくなっていた。体のどこかが激しく痛んでいた。後頭部を触ると、指先が血に染まった。彼女に突き飛ばされた拍子にぶつけた傷だった。・・深い疲労の底に屈辱に似た感情があった。何という一日だったのだろう。そう呟きながら私は、まだ、人がまばらな中央線に乗り込んだ。
|
|
|
|
|
|
 |
|