 Boxing Novelette ボクシング短編小説 Boxing Novelette ボクシング短編小説

|
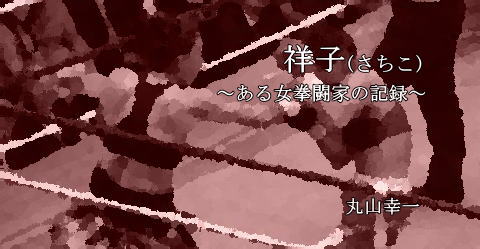 |
5
もう2時間が過ぎていた。殺伐とした部屋の中で私の心も冷えていた。
その私を、祥子の涙が止めた。
「結局、何を言いたいの?」詰問口調になりかけた私に、祥子が言う。
「あたし、あるときから、犬のように扱われ出したんです」。
祥子の話を総合すると、こういうことだった。――それまで二人のセックスは概ね、祥子が想像していたような内容だった。けれども2ヶ月ほどしてから、セックスの中味が露骨に変化した。自分に未練があることを十分に悟っていた高井が要求したのは、これまでとは全く別の体位だった。二人のセックスは接吻もなく、背後から挿入するスタイルだけになった。
「それだけじゃ、ないんです」。祥子が怒りに満ちた形相で言葉を継いだ。
「ある日、あたしが部屋にいると、高井が同僚を連れてきたんです」。その男は祥子がよく見知っているAジムの日本ランカーだった。男が笑いながら言った。
「高井から聞いたのだけど、もっとセックスを探求したいんだって?俺でいいのなら協力するからね」
「あたしはその言葉を聴いて頭が真っ白になって・・。でも次に感じたのは怒りよりも激しい屈辱でした。ドアの近くにいた高井を押しのけて部屋を出てから、どこをどう歩いたのか分からない。気がつくと、後楽園ホールでした」
ホールに足が向いたのは何故だったのか。疑問に思った私は祥子に聞いた。ボクサー二人に侮辱され、猛烈な屈辱感を抱いたのに、彼女は何故、ボクシングのメッカである後楽園ホールに辿り着いたのか。当時、19歳だった彼女にとって、ボクシングそのものへの嫌悪感が湧き起こるのが、むしろ自然だからである。
「分からないけど、あたしがあの屈辱を忘れさるには、自分がボクサーになるしかない、そう感じたからだと、今は思っています」
「強いねえ」。私は率直な気持ちでそう言った。実際、それから5年近くの歳月が経った今、彼女はまだAジムで汗を流し、スパーで4回戦ボーイを叩きのめしているのである。そして高井はとっくに引退していた。
既に初夏の夜が白んでいた。
「君の強さの原因が分かった」。帰り支度を始めた私に、祥子が言った。
「まだ話は終っていないんです」
「待ってくれよ」。うんざりした気持ちを露にした私に彼女が取ったのは、私が考えてもいない行動だった。それまで着ていた薄いブルーのカーディガンを脱ぎ捨ててブラウス一枚になった祥子は、私の目を見ながら言ったのだ。
「あたしの体を触ってください」
|
|
|
|
|
|
 |
|