 Boxing Novelette ボクシング短編小説 Boxing Novelette ボクシング短編小説

|
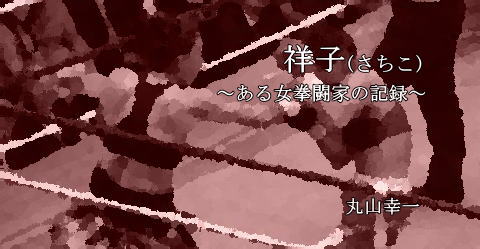 |
15
気がつくと雪がやみ、真っ白に覆われた街の底を這うような風が吹き付けていた。
やがて夜が白み始めた。私は朝ぼらけの街の中で凍てつくような風を受けながら、1時間前のことを思い浮かべ、そして自分自身がとった行為に打ちのめされていた。
女の頬を打ったのは初めてだった。祥子がもし一度でも私の手を払いのけようとしたなら、私は打つのを止めていただろう。けれども彼女は、無表情でじっと耐えていた。その祥子に覚えたのは、狂おしいほどの愛おしさだった。同時に微かな快感が私の体を走った。また打った。その私にさらに芽生えてきたのは殺意だった。「殺してやりたい」。自分の感情が言葉になって突き上げてきた。私は慄然とした。こうしてやっと、彼女を打つのを止めた。そんな自分自身に、私は打ちのめされたのだった。
この私は何者なのか。じっと耐えている女の頬を強かに叩き、快感を覚え、殺意まで突き上げてきた自分は一体、何者なのか。
そう考えた時、私の大学時代の友人が2年前に言った言葉がやっとわかった気がした。祥子との経緯をかいつまんで話した私に、ドストエフスキーの研究家である彼が口にしたのは、「お前はムイシュキン公爵には決してなれない男だからな」、というセリフだった。
彼が言いたかったのは、自分本位で他人の苦しみなど斟酌しようとしない私への糾弾だった。空想の中で私は、自分に問うた言葉を彼に向けた。「では俺は一体何者なのだ」。冷やかな笑みを称えた彼が答えた。「卑劣漢さ。お前は絶望のできない男だ。いや、絶望の意味さえ知るまい。生きることの意味も求めようとせず、いたずらに時間を過ごしているお前に、絶望の意味などわかるはずがない。そのお前こそ、卑劣漢ではないか」。そう言うと、ドストエフスキー研究家は姿を消した。
あの雪の日から私は、祥子からの連絡を待った。彼女がどこに泊まっているのかも知らなかったからだ。
それから2週間が過ぎた深夜に電話があった。「こんな時間に申し訳ありません。僕がわかりますか?」。聞き覚えのある声だった。高井だった。高井と認めた私に、彼が言った。「実はお会いしたいのです」。「いつ?」。「出来ればすぐにでも」。高井と私は、彼がタイトルを獲得した直後に取材のために何度か会っていた。それから4年ほどして、私は高井が祥子を陵辱し、彼女の人格をずたずたにしたことを知った。けれども私は、何故か彼に懐かしさを感じていた。
翌日の夜、私はかつて彼を取材したジムの近くの居酒屋で会った。席に着くとすぐに、高井が唐突に切り出した。「丸谷さんが祥子に会ったという日の夕刻に、彼女が僕のアパートを訪ねてきたんです」。
そんな気が、私もしていた。
「顔が腫れていただろう」。
「ひどいものでした」。高井は小さく笑いながら続けた。「で、僕にあなたを処罰してくれと・・・」。
「処罰?」。
「ええ、自分をこんな目に遭わせたあなたに苦しみを与えてくれって・・・」。
「で、俺を殴りにきたのか」。警戒心を露にした私に、高井が言った。
「いえ、その夜、祥子は泊まっていったのですが、翌日になると、けろりとして“もういいわ”っていうんです」。
「で、なぜ君は俺と会いたいと思ったの?」。
「彼女のことが、いまだにわからないからです。ただ、なぜあなたが彼女を叩いたのか。あなたとはそんなに深い間柄だったのか、と思うと何というか、奇妙な気持ちが突き上げてきて・・・」。
「冗談じゃない。祥子を叩いたのは事実だけども、手を握ったことさえない」。呆れながら答えた私に、高井が疑いの眼差しを向けた。
「じゃあ、祥子のお腹にいるのはあなたの子じゃあ、ないのですか」。
|
|
|
|
|
|
 |
|