 Boxing Novelette ボクシング短編小説 Boxing Novelette ボクシング短編小説

|
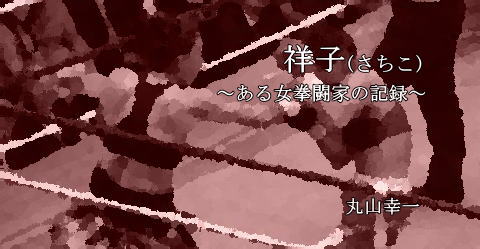 |
1
今から20年前ほど前になるだろうか。何かネタはないものか、とAジムを訪ねた時のことだった。ボクシング・ライターとして生計を立てている私に、寒川マネジャーが声を掛けてきた。
「面白い子がいるのだけど、よかったら書いてよ」
聞けば、18,9の頃から5年間もジムに通い詰めている女性で、ことあるごとに「プロになりたい」と寒川に訴えているのだという。
「そんな女、他のジムにいくらでもいるよ」と私がそっけない返事をすると、寒川は「いや、それがさ、この前、4回戦のフライ級とスパーをやらせたら、ものの見事に右のカウンターでダウンさせちゃったんだよ」と言った。
「そりゃ、やるね」と答えた私に寒川は「今日もスパーやる予定だから見ていかない」と言葉を継いだ。
女の練習生と男のプロをスパーさせていいものなのか、と思いながら佇んでいた私は、突然、面長で目鼻立ちの整った美女と目が合った。それが、寒川が話していた佐川祥子だった。寒川は「スポーツ紙や専門誌に書いている丸谷さん」と私を紹介し「祥子のこと、どうしても書きたいんだってさ」と勝手なことを言っている。
当時は米国内でこそ、すでに女性のプロボクサーが活躍していたが、日本では日本ボクシングコミッションもプロを認めていない時代だった。そして、何もボクシングの領域まで女性が荒らすことはないじゃないか、というのが私の偽らざる気持ちだった。
そんな私が何故、寒川の口車に乗って女性ボクサーを取材しなくてはならないのか。そう感じて憮然としていた矢先に肩を叩かれた。振り向くと、AジムのOBで、10年
ほど前に引退した元世界チャンピオンの友田勇二が立っていた。
「体がなまって仕方ないので、週に1,2度来て動いているんです。・・丸谷さんは誰の取材?」。口ごもっている私に「祥子を書いてくれるんだってさ」と、また寒川が言う。
「じゃあ丁度いい。実は今日、俺がスパーの相手するんです」。友田が祥子を指しながら、言葉を添えた。
こうなったら記事にするしかないか・・。しかし、私のそんな曖昧な気持ちは祥子と友田のスパーを見ているうちに吹っ飛んだ。前後左右と自在に踏むステップと鋭いジャブに感心していたのが1ラウンド目。2回。寒川が話題にしていた右が元世界王者の顔面にヒットすると、次の瞬間、友田の左瞼から鮮血が噴出したのである。
「あら、切れちゃった」。その友田の一言でスパーは即刻、中止された。
「世界チャンプをストップしちゃったね」と声を掛けた私に、祥子が傲然とした面持ちで言った。
「私に、記事にする値打ちを認めてくださいました?」
翌週のスポーツ紙に私は祥子のことを書いた。「俺が彼女に目をカットされたこと、絶対に書かないでね」という友田の強い要望もあり、私が書いたのは、次のようなことだった。――世界3階級制覇を達成した美男ボクサー・アレクシス・アルゲリョの芸術的なボクシングに魅了され、高校を卒業すると、母親の大反対に遭いながらもジ
ムに通い始め、毎朝15キロのロードワークと1時間のウエイト・トレーニング、週5日のジムワークを自らに課した結果、プロの4回戦を遥かに凌ぐ女性ボクサーが誕生した--。
記事が掲載されてから数日経ったある日、彼女から電話が入った。表向きは記事にしてくれたことへの返礼だったが、「あの内容では私という人間がほとんど伝わってこない」という不満が随所に込められた電話だった。
400字詰めの原稿用紙に直せば、3枚にも満たないもので、何でもかんでも載せられるスペースはない。私は「この女、何を言っていやがる!」という気持ちを抑えながら、そのことを斟酌して欲しい、そう弁明して電話を切った。
ともあれ、それでこの取材は終ったはずだった。 |
|
|
|
|
|
 |
|