 Boxing Novelette ボクシング短編小説 Boxing Novelette ボクシング短編小説

|
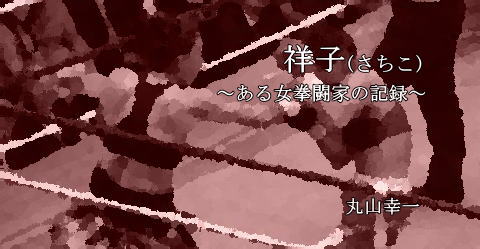 |
8
私の元に祥子からの封書が届いたのは平成元年の1月22日だった。
その日を明確に覚えていたのには理由がある。その日に、あの歴史に残る名勝負が、即ち、高橋ナオトがマーク堀越に挑んだ試合が待ち受けていたからだ。
私は封書を受けても、中味を開けようとはしなかった。もうこれ以上、彼女にかかわりあいたくない、という気持ち以上に、祥子という差出人の名前を見ただけで、私の自尊心が痛んだからだった。男に触られただけで生じる湿疹を見せるためだけに、私に自分の体を触らせた祥子。私をリトマス試験紙のように扱った祥子の神経が腹立たしかった。そこまで男に嫌悪を感じるようになった祥子に対する憐憫の情も、そのために私に助けを求めてきた切羽詰まった心も、私は忘れていた。恐らく、そうすることで私は自分の中の何かを守ろうとしたのだろう。私が自分の自尊心がいかに浅ましく、小さく、愚かなものであるか、という事実に突き当たったのはそれから随分、後のことだった。
1月22日。私は、はやる気持ちを抑えながら自宅を後にした。マーク堀越は青森県の三澤基地の米兵で、昭和62年の1月に日本スーパーバンタム級王座を獲得すると、以後6度の防衛戦をいずれもKOでクリアした最強の王者だった。高橋はその1年前、島袋忠に日本バンタム級王座を明け渡した後、スーパーバンタム級に転級。3連勝(2KO)を記録し、天才復活を印象付けていた。このカードがどれほど話題を呼んだのか。それは薄暮の時間ながら日本テレビがライブで放映したことでも分かるだろう。
当日売りのチケットは試合の3時間前に完売となり、試合開始の時間が近づく頃には、後楽園ホールはトイレにも行けないほどの混雑でごった返した。僅かな余地を見つけて座り込んだ記者席の右隣には、ボクシング記者界の大御所の芦沢清一さんが無言のまま陣取り、左の席には、元スポーツ報知の運動部長で当時は高質なノンフィクションを幾つも書き下ろしていた佐瀬稔さんが、二人が登場する前の誰もいないリングを祈るような表情でじっと見据えている。そして私も、その二人以上に緊張し、体を硬くしたまま、数分後に控えたゴングを待っていた。
マークやや優勢で始まったタイトル戦が大きく動いたのは4回だった。ラウンド中盤過ぎに高橋の右がマークのアゴを明確に捕えたのだ。次の瞬間、マークの体はニュートラルコーナーまで弾き飛ばされ、そして腰から崩れ落ちていった。ダウン! 8カウントで立ち上がったマークをさらに高橋が追い詰め、2分過ぎ、この回2度目のダウンを奪う。が、それから体を接してパンチを防ぐ王者を21歳の挑戦者は捕えることが出来ない。それでも、後楽園ホールを埋め尽くした殆んどの観客は、高橋の勝利を確信したことだろう。だが、続く5回に追い打ちをかけられず、王者を休ませてしまったことが、このタイトル戦を歴史に残るドラマへと変えていくのである。
6、7回と蘇ったマークの左右フックが再三、挑戦者にヒットすると、その都度、高橋の膝が揺れた。そして8回。マークの痛烈な右が挑戦者のテンプルを捕えると、高橋はそれまで耐えていたダムが、一挙に決壊するように前のめりに倒れていった。
島川威主審のカウントが5を数えた頃だった。冷静沈着をモットーにしている芦沢さんが叫んだ。「立て、立て!高橋、立て!」。あたかも天空まで届くような悲痛な声が途切れたとき、高橋は立った。が、その下半身は夢遊病者のようによろよろと揺れていた。この高橋に決着を急ぐマークがラッシュする。
試合後、この8回のシーンに報道陣の質問が集まったが高橋から返ってきたのは「僕、ダウンなんてしたんですか?」という言葉だった。つまりそのとき、彼の意識は既に失われていたのである。
マークの猛攻にさらされながら、意識が途切れた状態で繰り出した高橋の左フックは、しかし、的確で鋭かった。一転してマークの目が宙を彷徨いだす。そして9回。自ら窮地を救ったその苛烈な左の後に飛んだ右が、マークのアゴにヒットしたのは回の中盤だった。
次の瞬間、マークの体はリングに叩きつけられていた。それでも立ち上がったマークに高橋が追撃の左右フックを見舞うと、主審がスタンディングのダウンを宣言。そのまま10カウントを数えきり、試合は終った。
左隣りから「う、う」というすすり泣きの声が漏れてきた。声の主は佐瀬さんだった。私も誰かに背を叩かれれば、両の目から涙が溢れ出していたに違いなかった。
|
|
|
|
|
|
 |
|