 Boxing Novelette ボクシング短編小説 Boxing Novelette ボクシング短編小説

|
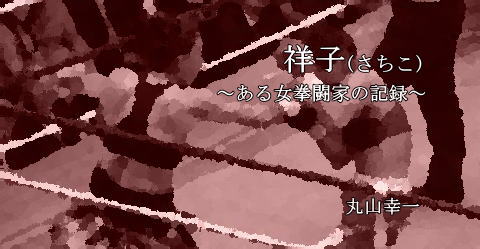 |
10
高橋ナオトがマーク堀越を大逆転のKOに屠り、天才復活を印象付けた夜の至福の瞬間。その時間を愉しんでいた私の背後で、祥子は一人静かに座っていた。
その祥子の存在がわかったのは、背中に視線を感じた私が振り向いたからだった。目と目が合ったにもかかわらず、私は直ぐに何事もなかったように、首を元に戻した。冷ややかな感情が私を支配した。
それにしてもあの祥子の眼差しは何だったのか。祥子とその居酒屋で出くわしたのが偶然であるはずがなかった。後楽園ホールを後にし、皆と連れ立って酒場へと急ぐ私達を、そっとつけてきたのに違いなかった。そして高橋の勝利に沸き返る私達の言動を、背後からつぶさに眺めていたのだろう。しかし、私が祥子に見た何の感情もない、あの二つの目は何だったのか。翌朝、高橋の快挙を反芻しようとした瞬間、私を突き上げてきたのは、祥子の眼差しだった。反射的に私の手は祥子から送られてきた、未開封だった手紙を探していた。祥子の手紙はこんな風に始まっていた。
「自己愛って、誰にもあるものだと思います。自分を愛することが出来なければ、人間は生きて行くことは出来ませんから。でも、その自己愛って、何なのでしょう。誰にも愛されない自分、そんな自分を人間は愛することが出来るのかしら。人間って、人から愛され、認められ、求められる自分しか愛することは出来ないのじゃないかしら。そうなら人から愛されることを知らない人間が、どうして自分を愛することが出来るのかしら。私は高橋ナオトさんとマーク堀越さんの試合をぜひ、見ようと思ってチケットを手に入れました。負けても、負けても、高橋さんって、人気があるでしょう。その高橋さんをどうしても見たかったのです。ファンからあんなに愛される高橋さんの試合を、もう一度、後楽園ホールで見てみたかったんです。……もしお時間があったら、丸谷さんとお話がしたい。高橋さんが勝つにしろ負けるにしろ、丸谷さんとお話がしたい。私は近々、ロサンゼルスに旅立ちます。そこでボクサーとしての自分を試したいと思ったからです。その前に一度、お会い出来れば、幸せだと……」
Aジムのプロだった高井に深い屈辱を味わわされた祥子は、通勤電車の中で男の手が僅かに触れただけで、激しい湿疹が出来るような体になっていた。その心の傷は、リトマス試験紙代わりにされた私自身が一番、知っていた。でも彼女はそれだけの理由で、自分を誰からも愛されない人間、社会から疎外された存在と感じるようになってしまったのか。私はそこまで考えて、再びきのう出合った祥子の眼差しを思い浮かべた。それは虚ろで、恰も死んだ魚のような目だった。
|
|
|
|
|
|
 |
|