 Boxing Novelette ボクシング短編小説 Boxing Novelette ボクシング短編小説

|
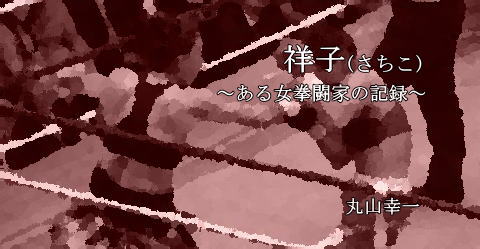 |
22
酒場まで30分ほどだった。酒場の一番奥にタンブラーを手にした高井がいた。私を認めると高井は手を挙げて、自分の席を指さした。黙って座った私に高井が笑みを浮かべながら言った。
「来てくれると思いましたよ」。
その意外なほど快活な声を聞いて、私がタクシーの中で思い当たった疑念は確信に変わった。
「祥子が身籠った子の父親は君なんだろう」。
私の強い口調に高井は「とっくに分かっていると思っていたのですがね」と応じた。
「俺は、俺達の間で起こったことのすべては、精神を病んでいた祥子自身に原因があると考えていた。しかし、実際は祥子が俺に語ったことが事実だったのか」。
興奮した私をなだめるように高井が言った。
「祥子が精神を病んでいたのは事実ですよ。実際、長いこと精神病棟に入っていたのですから」。
「さっき、電話で泣きながら自分も死にたい、と言ったのは嘘だったんだな」。
「本当ですよ」。そう言いながら彼は笑みを浮かべた。
「何故、俺を呼んだんだ」。
「無論、あなたとこの切ない夜を共にしたかったからですよ。できるなら、彼女を『境界性パーソナリティー障害』の病名の元に、精神病棟に閉じ込めた矢嶋先生も呼びたかった。3人で悲しい彼女の死を悼みたかった」。
その言葉に私は我を忘れた。そして高井の胸倉を掴んでいた。その私の下で高井の冷やかな目が光っていた。
かつてのチャンピオンは私の腕を捻るようにすると、静かに言った。
「あなたは僕を卑劣漢と言いたいのだろう。でもそれはあなたも同じですよ。それに祥子の死に一番責任があるのは、あの母親だ。キリストが説いたのは愛だろう。それなのに、あの母親は、幼なかった祥子を抱き締めることもしないで、ひたすら、厳格この上ない毎日を送らせてきた。そのあいつは何なんだ」。そう言うと割れんばかりにテーブルを叩いた。
その光景を見ながら私が感じていたのは、高井の心の闇だった。そして思った。最も精神を病んでいたのは、実は高井だったのではないかと・・。高井が再び笑みを浮かべて言った。
「でも祥子が死んで、あなたもほっとしたはずです」。
私は高井の言葉に、何も言い返せなかった。
高井の元を去り、家路につきながら、私は考えていた。半年前、私と別れた祥子は日を置かずに高井に会いに行ったのだろう。その祥子を高井はどう扱ったのか。恐らく高井は、祥子の母親と同じように、愛することができない人間に違いない。
では私はどうなのか――自分にそう問いかけた時、私は祥子の死にほとんど、心の痛みを感じていない自分を知った。さらに心の中で開放感を覚えている私自身に突き当たって、思わずゾッとしたのだった。 (了)
|
|
|
|
|
|
 |
|