 Boxing Stories �@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�{�N�V���O�l Boxing Stories �@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�{�N�V���O�l
|
|
story #�P |
 |
|
�Γc���T�@
�A�����J���E�h���[�������݂� |
|
���E�{�c�L���q |
�Γc���T�����X�x�K�X�ő�ԋ��킹�������Ă���A4�������߂����B
���A�ɉ���KO���̉f���́A���x���Ă������B�����ĉ��x���Ă��A���̎����̖���ʊX�֔�Ȃ��������Ƃ��A�S��������Ȃ�B
�X�[�p�[�E�F���^�[���œ��m�����m�A���{�A������WBA���E�b�艤���𐧂����d�ʋ��{�N�T�[�̃A�����J�E�f�r���[�킾����4��9���̃W�F�[���Y�E�J�[�N�����h��B
���̔��N�O�Ƀ��L�V�R�ŁA�g�J�l���Z�h���S�x���h�E�A���o���X�ɎߑR�Ƃ��Ȃ������WBA�b�艤������������̍ċN�킾�������A�x�K�X�ɂ�����Nobuhiro Ishida�͂܂������̃A���_�[�h�b�O�������B�OWBO�k�ĉ��҂�26��S��(24KO)�̃z�[�v�ƁA�O�b�萢�E�`�����s�I���Ƃ͂�����т�30��22��(7KO)6�s2���Ɩ}�f�ƌ��킴��Ȃ��V�Q�҂̓q�����́A17.5�P�B�܂�A�Γc��100�h���q����A1750�h���ɂȂ��Ė߂��Ă���Ƃ������Ƃ��BKO�����A�܂��ď���KO�����ɓq�����肵�Ă�����A�����������{�ɒ��ˏオ���Ă������Ƃ��c�B���ۂɂ��̒��匊���Ă�����|�|���̃f�B�t�F���X�}�X�^�[���ʊ��ɃV���[�g�p���`��_���A�ːi���Ă���Z��̃T�E�X�|�[��3�x�|����112�b�ɑ勻�����AMGM�O�����h�E�K�[�f���̑劽���̐U����̊��ł�����ɁA���������������Ԃ������ƂɂȂ�B
�������A�������������n�ɂ����Ƃ��āA�ʂ����Ăق�Ƃ��ɃX�|�[�c�u�b�N�̃J�E���^�[�ŁuIshida��KO�����ɁI�v�ƁA�S�O�Ȃ�100�h���D�������o�����Ƃ��ł������낤���c�B
���̋L���ɂ͐��N�O�A�A���}���h�E�T���^�N���X�Ƃ̃X�p�[�ŁA�{�f�B��@����ăR�[�i�[�ł��Ⴊ�݂��Γc�̎p���Ă��t���Ă������A���̊C�O�����������O��Ń`�����s�I���Ƃ��Đ�������́u�U�߁v�ɕ�����Ȃ��������Ă�������A�ǂ����Ă������̓C���[�W�ł��Ȃ������̂��B
�u����́A�ق�܂ɏ����Ȃ������������ł��B�����̓A�����J�Ő키���Č��߂āA�����Ȑl������������c�c�g���[�i�[�����f�B���m��������B��������̐l�����{���牞�����Ă���Ă��āALA�ł��������Ă���Ă���B���f�B�ɂ́g����������{�ɕԂ��Ȃ��h���Č���ꂽ��ł���v
WBA�^�C�g������������A�ċN�����߂��Γc�͎�����ڂ����ӂŁA���łɓ���݂ɂȂ����L�����v�n���T���[���X�ɓn�����B�g�g���[�i�[�h�Ƃ͂S�N�O����R���r��g��ł��郍�T���[���X�ݏZ�g���[�i�[���ӑ��A�g���f�B�h�͓��{�ł����Ȃ��݂̃��f�B�E�G���i���f�X���A���ӎ���10�N���̎t���ł�����B�����āg�m������h�Ƃ́A���܂��Ȃ��L������A�����J���C�݂ɓn��A�����I�A���{�������Ă���{�N�T�[�̐��b�l�����Ă����}�l�[�W���[�̃m�����J���B
���܂��܂ȏ�ǂ��N���A���Ȃ���A���̃`�[���̓J�[�N�����h��ɓ��B����B
�������߂��Ȃ�������A���ӎ�����d�b���������B�u���Ă��v�B�Γc�̎�C���悭�m��g���[�i�[�������̂�����A�����̊Ԃɐ[�߂��������鎩�M�Ȃ̂��Ƃ͎v�����B
���Ƃ��ƃ}�j�A�̉��ӎ��́A�h���E�J���[��w�i���E�G���i���f�X�Ƃ������g�p���`�������Ȃ��I��h���A�C�h���ŁA�Γc�̃X�p�[�����O�����߂Č��������炻�̃{�N�V���O�Z���X�ɍ��ꍞ�B�u�Γc�N�ɂ́A�p���`�������Ȃ��_�l�����Ă��ˁv�Ƃ������̃g���[�i�[�̌��t���āA��N��̐Γc�͐搶�ɖJ�߂�ꂽ�q���̂悤�ȏΊ���݂����B�Ȃ��f�B�t�F���X�ɍS��̂���q�˂�ƁA��l�̂������͓������B�u�����āA�ɂ��̃C��������v�B
�������A�A�E�F�[�̃����O�ł́A�U�߂Ăǂ�ǂ�A�s�[�����Ȃ���A�|�C���g�ɂ͂Ȃ�Ȃ��B���L�V�R�̓�̕��ɂȂ�ʂ悤�A���Ӄg���[�i�[�͐Γc�ɍU���̏d�v����������B��w�̂���Z�I�h���Z��̋��Ŏ҂Ƒΐ킷��̂�����A�����g���Ă����A�Ƃ����̂��퓅���낤���A�����ł͐Γc�Ƀ����O�̐^�Ő키�悤�w�������B���[�v�ɋl�܂邱�Ƃ��Ȃ��悤�����O�����ɐw���A�p���`���܂Ƃ߂�̂ł���B
�u�O���l�̓����O�ɏオ�������_�Ń|�C���g�����Ă�B�}�C�i�X����̃X�^�[�g������B1�����Ă���������_���B4��5���܂Ƃ߂ē��ĂĂ���ƃ|�C���g�ɂȂ�B���v����A�Γc�N�̋t�����c�[���A��ɓ�����B�ڂԂ��ĂĂ��A�����邩��v�B�g���[�i�[�́A�͋����A�����̂Ȃ������̌��t���A35�ŏ��߂ă{�N�V���O�卑�A�����J�̃����O�ɏオ��{�N�T�[�ɁA�V���n���J�����邱�ƂɂȂ�̂ł���B
�J�����ɉf���o���ꂽ�O�b�艤�҂́A���R�Ƃ����\��ŐR�[�i�[�ɗ����A�ԃR�[�i�[�����߂Ă����B
�S���O����ƁA�D���������J�[�N�����h�����M���X�ɏo�Ă������A�Γc�͓����Ȃ��B�����ĂقǂȂ��A���[����э������Ƃ��鑊��ɉE���J�E���^�[�B�z�[�v�͉����N�������������ʂ܂܃L�����o�X�ɗ��������B���g�̓��{�l���K�b�c�|�[�Y�����ăj���[�g�����֍s���B�ĊJ��A���K�����Ƃ����t�����c�[�A����Ƀt�H���[�̉E�Ń_�E����lj��B�����ă����c�[�łƂǂ߂̃_�E����D���̂ł���B���t�F���[�́A�X�g�b�v�ɔ[���������Ȃ��l�q�Łu�܂��o�����v�Ƒi����J�[�N�����h�Ɏ��U���āA�R�[�i�[�֖߂�悤�������B
�킸��112�b�̎����A�����Ă��̌�̌����̊ԁA�����̃A�i�E���T�[���勻���������B���Ȃ��Γc�̃f�[�^����g���āA��A�b�v�Z�b�g����Ă����B
�u�����̂��ƁA�����O����~�肽��l�������Ă��Ă����ւ�������ł���B�L�҂̐����������āB�܂�Ŗ����d�Ԃ݂����ł����i�j�v
���X�x�K�X�ł���Ȃӂ��ɑ劽���ɕ�܂�邱�Ƃ��A�����炭�{�N�T�[�Ȃ�N�ł�������̂��낤�B�����̓e���r�̌������ɂ��邱�����т₩�ȃ{�N�V���O�r�W�l�X�̒��S�ŁA���ڂ𗁂т���A�ǂꂾ���C�����������낤���B
�Γc�ɂƂ��Ă��A�Ђ����ɑz���Ă������̏ꏊ�������B
������R�A���o�����J������A���߂ă��X�x�K�X�ɏo���������̂��̂����A���̒��̈ꖇ�ɐΓc���f���Ă����B2003�N3��1����WBA���E�w�r�[���^�C�g���}�b�`�A���C�E�W���[���Y�E�W���j�A�W�����E���C�X��̑O���A���C���X�g���[�g����O�ꂽ�����h�J�W�m�ōs��ꂽ���[�J���t�@�C�g���ϐ�ɍs�������̂��̂ł���BLA�����_�Ƃ��Ă����ێR��q�ƃx�K�X�̐l�C�҃������_�E�N�[�p�[�̍Đ�B����ŋ͍����蕉�����i�����ێR�́A���̓��X�^�[�g����ҍU�����������B���A�n���̐l�C�E���͂����˔������N�[�p�[�̓I�m�ȃp���`��f���I�ɔ�e���A���t�F���[�E�X�g�b�v�B���������̏u�ԁA�n���q���C���̏����ɂ��ւ�炸�u�[�C���O���N�����B�X�g�b�v�͑����A�Ƃ����̂��낤�B�E���ɐ킢�A���O�̔s�k���i�������{�l���q�{�N�T�[�́A�����O�ォ��T�����܂Ŕ���Ō�����ꂽ�B�Γc�͂���ȗl�q���q�ȂŌ��Ă����B
�����̔ނ́A�s�U�̒��ɂ����B�f�r���[����10�����A2001�N3����6��ڂœ��m�����m�X�[�p�[�E�F���^�[���^�C�g�����l�������Ƃ���܂ł͏��������������B���A2������A�G�n�E�l���Ŏb�艤�ҁE�|�n�����Ƃ̓����ɂ܂����̔��蕉�����i���Ă���A���Ԃ��������B���{����������AOPBF�����Ԃ�炫�ɂ����s�ɏI���B
�u�������������ɁA�h�������������A�������A�Ȃ�Ƃ�����ȓW�J��ς������Ǝv���āA���߂ăA�����J�ɗ�����ł���ˁB�g���[�j���O�̂��߂Ƀ��T���[���X�ɗ��āA���߂ă��X�x�K�X�Ń{�N�V���O�ϐ�B�q�Ȃ��烊���O�����Ȃ���A�g�����������Ŏ����������Ȃ��h���Ďv���܂����v
�N���������ł��閲�ł͂Ȃ��B�s�U���o���A���E�������l���ĒD���āA8�N�z���ŁA���̓���̒n�ɗ������B�������A����MGM�O�����h�B�����h�}�C�P���E�J�c�f�B�X�����C���A�Z�~�ł͂��̃G���b�N�E�������X���}���R�X�E�}�C�_�i�Ƒΐ킷��A�S�[���f���{�[�C�v�����[�V������Ë��s�̑O���ł���B
�u�~�[�n�[�Ȃ�łˁc�l�i�j�قƂ�ǂ���낫��낫��낫��낵�Ă܂����ˁB���킟�A�N������A���āB�ł����͕��ʂȂ�ł���BMGM�ł��A�������x�������ɂ��Ă邵�A�����ɂ��Ă���Ă悩�����ł���B�g���肾�����āh���Č����āA�l�͏W�����邱�Ƃ��ł�����ł��B�g�����h�A���Ă����C�����ɂˁB�������v�ł���A�|�[���E�E�C���A���X�ł��Z���q�I�E�}���e�B�l�X�����Ă��v
���ꂩ��ANobuhiro Ishida�̖��O�͊ԈႢ�Ȃ��A�b��^�C�g����ێ����Ă���������������ƕp�ɂɃ��f�B�A�ɓo�ꂷ��悤�ɂȂ����B
���{�����\�L�̑�k�ЂɌ������Ă���1�������炸�B���{�l�̊撣��ɐ��E�����D���������𑗂��Ă�������������A��ΓI�s���̗\�z�����x�K�X�V�Q�̒j�ɂ�Japan�fs Rising Sun,��Japanese Super-Hero�Ƃ������^���������B
�����āAWBC�~�h�������_�`�����s�I���̃}���e�B�l�X�⌳WBO�E�F���^�[�����҃E�B���A���X�A�܂��ŋ߂�WBC�~�h�������҂ɂȂ�������̃t���I�E�Z�T�[���E�`���x�XJr.�ƁA���̂�����̔e���𑈂��c�����m�i�����̐w�c�j�������A�ΐ푊��Ƃ��Č���WBA�X�[�p�[�E�E�F���^�[��2�ʁAWBC�~�h����13�ʂɃ����N�����Ishida�𖼎w������̂��B�����t�@�C�g�}�l�[�̊z�́A�J�[�N�����h������Ƀ[����������Ȃ����Ƃ����B
������̈ꏟ�ŁA���X�x�K�X�ɂ����Ắu�V�l�v�ł�����{�l���A�Z���u���e�B�ɂȂꂽ�킯�ł͂Ȃ��B
7��1������g���[�j���O�̋��_�ł��郍�T���[���X�ɓn�������A�_�c�郁�L�V�R�̐V���́E�J�l���v�����[�V��������̓r�b�O�}�b�`�ǂ��납���[�J���t�@�C�g����̒m�点���͂����A�Ȃɓ�l�̎q����C���Ă̒������ɕ��G�Ȏv�����������Ȃ���W���ŃX�p�[�����O���d�˂���X���߂����Ă���B���܂̂Ƃ���8��27���Ƀ��L�V�R�Ő킦��A��������Ȃ����A���ۃS���O����܂ł͂��A�L�����Z��������ɍ������邩�m��Ȃ��B����̃J�[�N�����h�����X�ƒn���e�L�T�X�ōċN���A7��23���̃A�~�A�E�J�[���U�u�E�W���_�[��̑O���ł����������߂Ă���̂�����A�L�͂ȃv�����[�V�����ɑ����Ȃ��O���l�ɂ͂�͂�A�卑�A�����J�͌������ƌ��킴��Ȃ��B
���A�ǂ�Ȃɏ����ȉ\���ł����Ă��A��������̍����炽������̖����E�L���̃{�N�T�[���A�����J�̃����O��ڎw���̂ɂ́A�����Ƃ����ɂ��������Ă��Ȃ��������邩�炾�Ǝv���B������A�傫���B�ǂ����M�����u������̂Ȃ�A������Α傫���q�����������ł͂Ȃ����B�����t�Ȃ�B
�m������́A����Ȗ����݂�{�N�T�[�������ԁA����葱���Ă����l���B
���T���[���X�̓_�E���^�E���̖k�̂͂���ɂ���g���g�E�L���E�ƌĂ��X�ŁAAnzen�i���S�j Hardware�Ƃ������������c��ł���B�䏊�����H��A���|�p�i�ȂǓ��{�̓`���I�ŕ֗��ȓ���ނ������܂��ƕ��X�ŁA���{�l�ł͂Ȃ����q�ɁA����̎g������������̕��@�܂Œ��J�ɉp��Ő�������D�����X��A�����i�̊炾�B���A�{�N�V���O�̎d���l�Ƃ��ẮA�m��ꂽ�Ƃ���ł́A�֓����ꂩ�牤����D�����V���b�g�K���E�A���o���[�h�A���f�B�ƃw�i���̃G���i���f�X�Z��A���R�����ƈ����������T�E���E�f�������Ƃ������I��̃}�l�[�W���[�ł���A�g���[�j���O�⎎�������悤�Ɠ��{�������Ă���{�N�T�[�̏h�̎�z��}�b�`���C�N�ɂ��ꔧ�ʂ��ł����B
60�N�ォ��70�N��ɂ����ẮA���{�l�����E�̈ꋉ�i�����������������x����������B1964 �N4���A�I�����s�b�N�E�I�[�f�g���A���ŊC�V�����K���G�t�����E�g�A���N�����h�E�g�[���X���͍�2�|1�Ŕj�������́A�q����\��i���j�I��ꂪ15���h�����̑��Q�������j���钆�A�����炪������B68�N�ɐ��鐳�O���I�����s�b�N�E�I�[�f�g���A���ł�4�A����o�ē��N9���Ƀ������A���E�R���V�A���Ń��E���E���n�X��卷����ŕԂ蓢���ɂ��A���{�l���ƂȂ�C�O�ł̐��E�����D��ɐ������������R�[�i�[�ɂ����B69�N6���ɉԌ`�i���g�A���N�����h�E�g�[���X�ɔ��菟�������߂�ԋ��킹���N�����A����5�N��ɃV�Q���R���̂��̖����҃_�j�[�E���y�X�������ɒǂ��������������A�I�����s�b�N�̏�A�q��������h���D���������l�q���A���̂����v���Ō��Ă����Ƃ����B
�u�{�N�V���O�͂ˁA�����Ȃ��A���Ďv����ł���A����ς�B�Γc�̎����ŁA�R�[�i�[���œ��̊ۂ�U���Ă���Ƃ��낪�e���r�ɂ����ꂽ�݂����łˁA���{�̌Â��F�l��������g���܂��܂��{�N�V���O����Ă��̂��h���ċv���Ԃ�ɓd�b���������Ă����肵�܂�����v
70���߂��A�D�X��R�́gAnzen�̃m������h�̃{�N�V���O�M���A�V�����q�[���[�̓o��ōĔR������B
�u������x�A�I�����Ă����ȁA���ĂˁA�v����ł���v
120�N�ȏ���O�A�V�V�n�����߂ĈڏZ���Ă������{�l������A�푈�̌����������z���Ė���ǂ������Ă����ꏊ�ł��郊�g���g�E�L���E�́A�T���ɂȂ������n�l�͍x�O�ւƎU�������A���Ă͖k�čő�̓��{�l�X�ŁA�푈�O���3���l���̐l����炵���������B���A����ȃo�X��Ԃ��������ق���������グ���ԃX�g���[�g�́A���̎Ќ��̒��S�������Ƃ����B�ʂ�̖k���Ɏc��Ԍ����������܂��܂��̑f���C�Ȃ�����̃r���͒����̂悤�ɘA�Ȃ�A����ɂ����Ă��ڂ�ɂ��ꂽ�悤�Ȃ������܂��Ȃ���A�������j�̏ؐl�Ƃ��ċB�R�Ƃ����ɗ����Ă���B�m������̂��X�͂��̒����̈�p�ɂ���A���̂��ߓ��{���痈��{�N�T�[�̑������A���̋ߕӂ̈��h�ɑ؍݂��Ă����B
����Ȓ��̈�A�_�C�}���z�e�����A�Γc�̒�h���B
�������炭�����Ă������{�l���قƂ�ǂ��Ȃ����[�����X�w�~�X�^�[���[�����x�̓�K�ɂ����āA��x���点�Ă���������Ƃ�����̂����A����Ă��������K���X�̔��������čׂ��K�i���オ�����Ƃ��낪�g���r�[�h�B������ƈ��z�̂悭�Ȃ������l�̂����Ǘ��l�̂��̃z�e���́A�g�C���A�o�X�͋����B���N�O�ɉ��������ĕǂȂǂ͏������邭�Ȃ��Ă��邪�A�V��͒�߂Ō��̓���Ȃ������������āA�����ɐQ���܂肵�Ȃ�����X�g���[�j���O�ɒʂ��{�N�T�[�̎p�������яオ���Ă���C�������B�Γc�͕������đ��ɖʂ����u�C���^�[�l�b�g�̎g���镔���v�ɕ�炵�Ă��āA�������蒇�ǂ��ɂȂ����Ǘ��l�̂����S�n��������Ă���邱�Ƃ�����Ƃ����B���A���͂���������ƁA�����Ȓn��ɋ߂��R�ԃX�g���[�g�ɂ���`���b�g�E�b�h�Ƃ����h�Ɉڂ낤���Ƃ��l���Ă���炵���B
�u�����オ�������A���V���H������Ȃ�łˁc�i�j�v
�Γc��b���Ă���ƁA�����Ɗ�p�ɁA���܂����̒���n���Ă����Ă��悳�����ȋC������̂ł���B
186�p�̒��g�ŁA���Ă̒ʂ�́g�C�P�����h�ŁA���g�b�v�A�}�Ȃ̂��B���A���M���X�Ɉ���Ă����̂��Ǝv���A�u�߂���߂����C�Ń}�C�i�X�v�l�v�B
�c��������i���Z�ɐe���ݑ��E�������Z����ɑI�����D���A�ߋE��w����ɍ��̏��D�����ʂ����Ă���B�ɂ��S��炸�A���ƌ�͈�x�A�O���[�u��݂邵���B�����{��{�݂̎w�����Ƃ��Ď��i�擾��ڎw���ĕ����Ȃ��瓭���Ă������A���Z�Ń{�N�V���O�����Ă���Ƃ����j�q���k�ɗ��K�����邱�ƂɂȂ������Ƃ����������ŁA�Љ�l�I�茠�i1998�N�j�ɏo��B���Ǝd���łقƂ�Ǘ��K�ł��Ȃ��܂܂Ń����O�ɏオ�������A���ʂ͗D���B���������̖��I��A�����I�s��j���Ẵ^�C�g���ł���B���N�̑S���{�I�茠�ł�3�ʁB�����m�����m�~�h�������ҁE�����K���̌Z�E�����ɔs�ꂽ�B2���E���h�̏I���Ƀ{�f�B�u���[����������Ĕ��蕉���B
�u�����ɕ������Ⴄ��ł���c�v����5�s������ԁA�����ɕ������Ǝv�Ă܂��B�Ƃɂ����ˁA�������M���Ȃ���ł��B�A�}�̍���KO�ERSC�������������ǁA�v���ɂȂ����玎������������A�X�^�~�i���S�z�ŁB������A�p���`�������Ǝv���Ă����b�V���ł��Ȃ���ł���A�X�^�~�i���S�z�₩��i��j�B�߂��Ⴍ����|����łˁc�B���A���ł��A������₽��K�[�h�����ł���B���ꂪ�悩����������܂����ˁA���������Ă�킯�₩��v
2007�N10���ɐ��E�����N��_���ăn�r�G���E�}�}�j�Ɛ키�O�A�m�l�ɉ��Ӄg���[�i�[���Љ��A���߂Ďt�������ׂ��n�Ă������A���̋L������������A�L�����v�����A�Γc�͂��̖ړ��Ẵg���[�i�[�ƑΖʂł��Ȃ������B��������Ƃ̂Ȃ��H���o�X�����p���ŃW���֍s�����Ǝ��݂����̂́A���G�Ȏ����\�𗝉��ł����A�Ȃ�Ƃ��ړI�n�ɂ��ǂ�������ɂ͗��K���I����Ă����c����ȋ�J�b�����悤�Ɏv���B
�������A�������������Ԃ�����ǂ����z�����肵�Ă������Ԃ�A�t���œ����l�̉����A��C�ŕ|��������F����j���������Ă������ɈႢ�Ȃ��B
�u6��ڂœ��m���l�������A������������낢���ȁA�Ǝv���Ă���ł���B����Ȃɋ�J����Ƃ͂ˁc�c�B�Ƃ�ł��Ȃ��������ł��ˁi��j�B�J�[�N�����h��́A���͔��Ȃ��炯�ŁB�������������B����������Ɨ��������Ă�������悩�����B�ł��c���܂𖡂���āA������߂�Ɗ撣�ꂽ��́A�ւ��Ƃ���ł��B�����Ȑl�ɏ����Ă�����Ă����܂ł�������B������l�������A�Ƃ��ɂ�߂Ă��Ǝv���܂��B�m�����ܗ����Ċ��ł��ꂽ�́A�ق�܂Ɋ����������ł��ˁc�B���邳���X�Ő��E�l�������̘b�Ƃ����Ă���܂����v
�@���X�x�K�X�ł̑�ԋ��킹�́A�ꎞ�̊�т⋻���͂����炵�����A���͐Γc�̐S�������̂ł͂Ȃ��Ƃ����B
�u�����܂�����A�ԋ��킹���܂�����A���X�x�K�X�ŁB�ł��A�܂�������Ȃ��B�A�����J���h���[���́A���ꂩ��ł��B�܂��܂��S�R�A�������ĂȂ���ł��B�g�b��h���Ă������t�A����Ȃ����B�����g�b��h���Č�����́A��������������ł���B�c�c�Ȃ�łł����ˁc�c���������A�Ȃ��Ȃ����e�ɔF�߂Ă��炦�������Ƃ������Ȃ�ł����ˁc�l�ɔF�߂Ă��炢�������Ă����C������������ł���v
�@���́A��������Ȃ��C������Q����S���������A�O�i�ł���B�����ďd�˂���J�̌��݂ƂƂ��ɁA�A�����J�Ŗ���ǂ����߂̗͂ɂȂ�̂��낤�B
�@8��18����36�ɂȂ����Γc���T�B�ނ̃{�N�T�[�l���́A���ꂩ�炪�����Ȃ̂�������Ȃ��B
|
|
|
|
 |
 |
 |
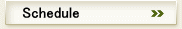 |
 |
 |
 |
 |
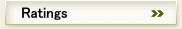 |
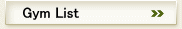 |
 |
 |
|
|
| ARCHIVES |
istory#1�@
�Γc���T
�u�A�����J���h���[�������݂Ɂv
by�{�c�L���q |
|
|
|
|
|